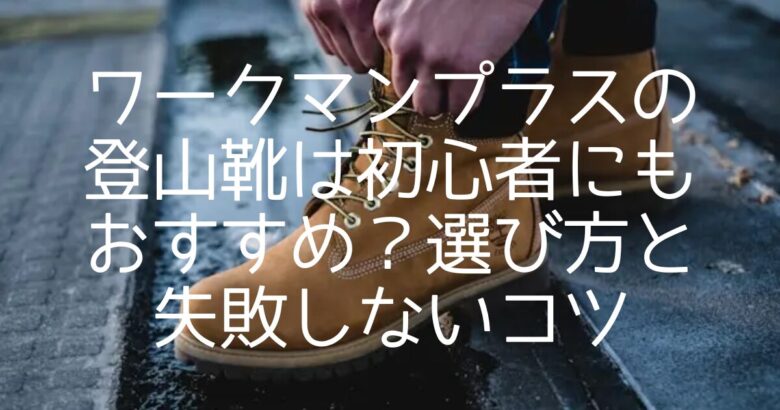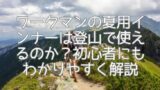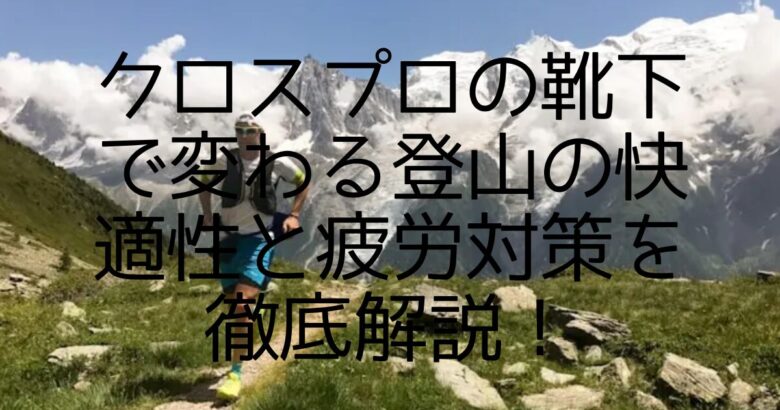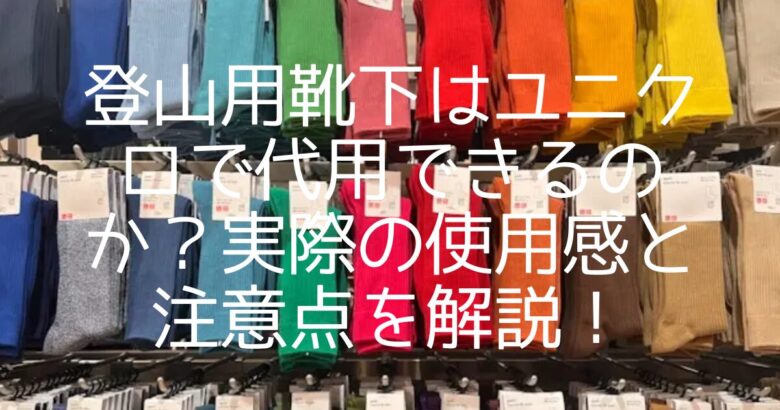登山やハイキングを始めたい方、または新しいシューズを探している方の中には、「ワークマン プラス 登山靴」と検索して情報を集めている方も多いのではないでしょうか。
ワークマンは、コストパフォーマンスに優れた登山靴を数多く展開しており、特に「アクティブハイク」「トレックシューズアジム」「トレックシューズエンリル」といったモデルは、それぞれに異なる特徴を持っています。
本記事では、各モデルの特性や向いている登山スタイル、寿命の目安やサイズ選びのポイントなどを解説します。初心者の方にはミッドカットタイプのメリットにも触れながら、最適な一足を選ぶためのガイドとしてご活用ください。
この記事でわかること
①ワークマン プラス登山靴の各モデルの違いや特徴
②使用シーンに応じたカット(ハイカット・ミッドカット・ローカット)の選び方
③登山靴のサイズ選びとフィット感の重要性
④登山靴の寿命やメンテナンス方法の基本
ワークマンプラスの登山靴の魅力とは

✅ワークマンのトレッキングシューズは何種類?
✅登山靴アクティブハイクの特徴
✅トレックシューズ・アジムの特徴
✅トレックシューズ・エンリルの特徴
✅各モデルをスペックで比較
✅防水性と透湿性を兼ね備えた構造
✅工夫を凝らしたアウトソール
✅クッション性の良いミッドソール
✅抗菌防臭機能「DEOPUT」が備わったインソール
ワークマンのトレッキングシューズは何種類?
登山歴4年の雑魚雑魚ですがおすすめの登山靴はワークマンのランシュー一択群馬のおすすめの山は谷川岳です!対戦よろしくお願いします🥺 pic.twitter.com/YGSO5hmX00
— れん (@xRENZAURx) January 9, 2025
現在のワークマンでは、登山やハイキングに適したトレッキングシューズが数多く展開されています。これは、利用者の体力や技術、目的地の環境など、さまざまな条件に応じて最適なモデルを選べるようにするためです。
例えば、ワークマンの代表的なモデルには「アクティブハイク」や「トレックシューズアジム」、さらに「トレックシューズエンリル」などがあります。
これらのモデルはそれぞれに異なる性能や構造を備えており、防水性や軽量性、耐久性などに重点を置いた作りになっているのが特徴です。用途に合わせてこれらを使い分けることで、登山をより安全かつ快適に楽しむことができます。
このように考えると、自分の登山スタイル、経験値、登山頻度などを踏まえたうえで、最適な1足を見つけることができる点は、ワークマンのシューズが支持される大きな理由の一つだと言えるでしょう。
登山靴「アクティブハイク」の特徴
ワークマンで、ハイバウンスとアクティブハイクを再調達(ΦωΦ) pic.twitter.com/Oh1xBHgd8T
— トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ (@shellingford221) March 17, 2024
「アクティブハイク」は、軽量でグリップ力に優れたモデルとして知られており、長時間の歩行でも足への負担が少なく、快適な登山体験が可能です。そのため、日帰り登山やハイキングといった比較的軽めのアクティビティに適しており、初心者にも扱いやすい点が高く評価されています。
ただし、ハイカットタイプではないという構造上、足首までのサポート力が十分とは言えません。そのため、岩場や斜面の多い山道では足をひねるなどのリスクが高まり、やや不安が残る場面も出てきます。足首のサポートを重視する登山者にとっては、この点をデメリットと感じる可能性があります。
このように考えると、「アクティブハイク」は登山の目的地やルートの難易度、自分の体力レベルに合わせて選ぶ必要があるシューズと言えるでしょう。適切な用途に使えば、非常に心強い一足になることは間違いありません。
トレックシューズ・アジムの特徴
ワークマン初のミドルカット登山靴「アジム」をGET🥾
— けー@薬物ダイエット中(合法)💊 (@sientalightblue) April 11, 2024
お値段なんと3,900円❗️
10年以上履いてた登山靴がダメになったけど、年に数回、軽登山する程度だから何万円もかけて買い替えるか悩んでたところでアジムに遭遇👀
噂では全国で40店舗くらいしか扱ってない激レア品っぽい
その実力は果たして😳 pic.twitter.com/q6CG4Vd6gp
「トレックシューズアジム」は、防水性と耐久性を兼ね備えたモデルであり、特に過酷な気象条件下での使用に適しています。雨が降る日やぬかるんだ登山道においても、足元をしっかり守ってくれるため、安心して山道を進むことができます。
また、防水機能に優れているだけでなく、泥や水の侵入を防ぐ工夫も施されており、シューズ内を常に快適に保てるのが特長です。
さらに、ソール部分には高いグリップ力を発揮する素材と設計が用いられており、濡れた岩場や傾斜のある路面でも滑りにくく、安定感のある歩行を実現します。長時間の使用でも足元がぶれにくいため、登山中の疲労軽減にも貢献してくれます。
このように考えると、「トレックシューズアジム」は、特に悪天候や滑りやすい道を歩く場面、あるいはやや難易度の高い登山ルートに挑戦する登山者にとって、信頼できるパートナーとなる一足だといえるでしょう。
トレックシューズ・エンリルの特徴
最近ワークマンから発売になったローカットのトレッキングシューズ"エンリル"を買ってきました。防水機能有りで、お値段は税込3500円。安っ!履いてみた感じは、普段SOTAの登山で使っているモンベルやon のトレランシューズとかなり似ています。明日、近くの山で使い心地を試してみるつもりです🐷 pic.twitter.com/VVC1zxSWUA
— JJ1PIG / さいたまNH113 (@jj1pig) September 28, 2024
「エンリル」は、軽量で通気性に優れており、暑さが厳しい夏場の登山やハイキングにぴったりのモデルとして、多くの登山者に支持されています。軽やかな履き心地と、ムレを防ぐ構造によって、気温の高い日でも足元の快適さを保つことができます。
また、履き口には柔らかい素材が使用されており、足首への圧迫感が少なく、長時間履いても足が疲れにくいという工夫が施されています。加えて、歩行時の足の動きに自然にフィットする形状も取り入れられており、よりスムーズな足運びが可能になります。
このように、快適性を何よりも重視する登山者にとって、「エンリル」は機能面と履き心地の両立が図られた理想的な選択肢だと言えるでしょう。
各モデルをスペックで比較
#ワークマン
— 🦅KEI♪オレンジの人🐝 (@KEI_PHOTO916) February 25, 2025
ワークマンのトレッキングシューズ
「トレックシューズ アジム」使ってみた感想
昨年9月から使い初めて、約5ヶ月程たったので改めてレビュー
・登山としてはドライで100~600m級までの軽登山では問題ない程度(但し、個人差あり)
・700m級以上になると登れなくはないが、疲労がヤバい pic.twitter.com/PkqOXU2fp8
登山靴を比較検討する際には、見た目や値段だけでなく、スペックや特徴をしっかり理解することが重要です。なぜなら、登山環境や使用頻度によって求められる性能が異なるためです。
以下の表に、ワークマンで展開されている代表的な登山靴3モデルを比較してみました。
| モデル名 | 重さ | カット | 特徴 |
|---|---|---|---|
| アクティブハイク | 軽量 | ロー | グリップ力◎・軽くて初心者向け |
| トレックシューズアジム | やや重め | ミッド | 防水・耐久性◎・悪路や長時間登山に対応 |
| トレックシューズエンリル | 最軽量 | ミッド | 通気性◎・夏場や日帰り登山に最適 |
例えば、「アクティブハイク」はローカットでとにかく軽く、動きやすさを重視したい方に人気です。日帰り登山や公園でのハイキングに向いており、気軽に履ける一足です。
「トレックシューズアジム」は、やや重めですが、悪天候でも安心の防水構造と高い耐久性を備えています。長距離や斜面が多いルートでその強さを発揮します。
「トレックシューズエンリル」は、汗をかきやすい夏場にうってつけ。通気性を最重視する方には見逃せない存在で、軽快に動きたいハイカーに向いています。
このように、ワークマンの登山靴はそれぞれの個性がはっきりしているため、自分の目的や登山環境に合ったモデルを選ぶことが、快適さと安全性の両立につながります。
防水性と透湿性を兼ね備えた構造
ワークマンの4500円の登山靴凄い
— ふみ △ (@DSC10th) October 19, 2024
全ての中華登山靴が駆逐される😂
6cm防水
透湿防水素材INAREM
トレックシューズアジム pic.twitter.com/jShK6yMWqI
登山靴において、防水性と透湿性のバランスは非常に重要な要素です。どちらか一方だけが優れていても、もう一方が不足していると、登山中の快適さが損なわれる可能性があります。これにより、疲労感が増し、思わぬトラブルの原因にもなりかねません。
例えば、防水性が高いだけの靴では、外からの水分は防げても、靴内部にこもった湿気や汗が逃げにくくなります。その結果、靴の中が蒸れてしまい、足に不快感を与えたり、靴ずれや水ぶくれなどの足のトラブルを引き起こす恐れがあります。これは長時間の登山で大きなストレスとなり、行動力の低下にもつながります。
このような事態を避けるためには、防水性と透湿性の両方を兼ね備えた素材を選ぶことが不可欠です。例えば、ゴアテックスのような機能性素材は、外部からの水を防ぎつつ、内部の湿気を効率よく外に逃がす構造になっているため、常に快適な状態を保ちやすくなります。
このため、登山靴を選ぶ際には、単なる防水性の有無だけでなく、透湿性も重視して製品を見極めることが、快適で安全な山歩きを実現する重要なポイントになります。
ワークマンプラスの登山靴は、コストパフォーマンスに優れたアウトドア用フットウェアとして人気がありますが、防水性と透湿性に関しては以下のような特徴があります。
✅ 防水性の特徴
独自の防水素材「DIAMAGIC DIRECT®(ディアマジックダイレクト)」や「FieldCore」シリーズなどを採用
これらは雨や雪などの水の侵入を防ぐ撥水・防水加工が施されています。
靴の構造自体も防水を意識
シーム(縫い目)を極力減らす設計や、防水フィルムを内蔵しているモデルもあります。
完全防水ではないモデルも存在
長時間の雨天登山やぬかるみを伴う環境では、ソールの接合部やアッパーの通気部分から水が侵入する可能性もあるため、過酷な環境下では注意が必要です。
💨 透湿性の特徴
透湿防水フィルムの採用(一部モデル)
ムレを軽減する透湿素材を使ったモデルでは、登山中の汗や蒸れを外に逃がす機能があります。これにより靴の中の快適さが向上します。
価格帯によって性能に差がある
透湿性の高い素材(例:GORE-TEX®のようなもの)は使われていないため、一般的な高級登山靴と比べると透湿性はやや劣ります。
蒸れやすい季節・環境では通気性重視のモデル選びが重要
軽登山や日帰りハイキングなどでは問題ありませんが、夏場や長時間行動する場合は靴下との組み合わせも工夫する必要があります。
工夫を凝らしたアウトソール
近所のワークマンに行ったら、普通にエンリル売ってた。
— すすむ (@Deandre70157784) September 20, 2024
雨の日用に一足ゲット。
アウトソールがアルトラみたい。 pic.twitter.com/fWI8CHKnI9
アウトソールは、滑りやすい場所や岩場での安全性を支える非常に重要なパーツのひとつです。登山中は、濡れた石やぬかるんだ道、斜面など、足元が不安定になる場面が多々あります。そうした場所でも滑らずにしっかりと踏ん張れるかどうかは、アウトソールの設計に大きく依存します。
ワークマンの登山靴では、独自パターンのラグ(突起)を用いることで、泥や小石が詰まりにくく、あらゆる地形で優れたグリップ力を発揮できるように設計されています。さらに、ラバーの硬さや配置も工夫されており、滑りやすい斜面や不安定な岩場でもしっかりと地面を捉えることが可能です。
このような構造によって、実際の登山時においても足元の不安を軽減し、滑りやすい状況でも安定した歩行を可能にしています。結果として、安全性だけでなく疲労感の軽減にもつながるため、アウトソールは登山靴選びにおいて注目すべきポイントと言えるでしょう。
クッション性の良いミッドソール
ミッドソールのクッション性は、登山中の歩行時に足にかかる衝撃をやわらげ、疲労を大幅に軽減する効果があります。
特にワークマンの登山靴に採用されているミッドソール素材は、長時間の登山やハイキングでも足の裏に過度な負担がかからないよう配慮されており、使用者にとって非常に快適な履き心地を実現しています。
例えば、舗装されていない山道や起伏のある地形では、地面からの反発力や突き上げによって足にかかる圧力が増す傾向がありますが、適度な弾力性と復元力を備えたミッドソールであれば、そうした圧力を吸収・分散してくれるため、登山後の疲労感を最小限に抑えることが可能です。
このため、体力に自信のない初心者でも、足への不安を感じずに安心して長時間の登山に挑戦できる環境が整っていると言えるでしょう。
抗菌防臭機能「DEOPUT」が備わったインソール
ワークマンの登山靴には、「DEOPUT(デオプット)」という抗菌防臭機能が備わった高機能インソールが採用されています。
このインソールは、登山や長時間の歩行といったハードな使用環境においても、靴内の不快な臭いをしっかりと抑えることができ、常に清潔で快適な履き心地を保つ効果があります。さらに、抗菌効果によって雑菌の繁殖を防ぎ、衛生的な状態を長時間キープすることができます。
例えば、夏場の高温多湿な気候での使用や、汗をかきやすい状況でも、靴の中の嫌な臭いが気になりにくくなるため、周囲への配慮も安心です。こうした点からも、登山やアウトドア活動において、このインソールの機能性は非常に心強い要素といえるでしょう。
このように、足元の清潔感や快適性を重視する方にとって、「DEOPUT」の存在はまさに嬉しい機能であり、快適な登山体験をサポートしてくれる大きな助けとなるはずです。
ワークマン プラス登山靴の選び方

✅登山靴はなぜハイカット?
✅初心者はミッドカットがおすすめ
✅ローカットはいつ履く?
✅何センチ大きいサイズがいい?
✅寿命は?・耐久性
✅ワークマンプラス登山靴の選び方:総括
登山靴はなぜハイカット?
登山靴がハイカットである理由は、主に足首の保護と歩行時の安定性を確保するためです。特に登山では、岩場や木の根が張り巡らされた不整地を歩くことが多く、そのたびに足元が不安定になる危険性があります。
例えば、こうした状況では踏み外したり、足をひねったりするリスクが高まりますが、ハイカットの登山靴であれば足首までしっかりと覆われており、左右のブレを抑えて関節を固定する効果が期待できます。これにより、ねんざの予防につながり、安全性が大きく向上します。
このような理由から、本格的な登山をする人や、より険しい山道に挑戦する際には、足首をしっかり守れるハイカットタイプの登山靴が非常に推奨されているのです。足元の安定感は体全体のバランスにも影響を与えるため、登山の快適さと安全性を高めるためにも、重要な選択ポイントとなります。
初心者はミッドカットがおすすめ
今までワークマンの¥1900靴で登山してたけど、思い切って¥16000でミドルカットの靴買った pic.twitter.com/BJxbZjTfas
— いちご (@ichigo_No213) June 5, 2022
登山初心者には、ハイカットほど重量感がなく、ローカットよりも高い安定性を持つミッドカットの登山靴が非常に適しています。
これは、足首のサポートをある程度確保しながらも、重すぎず動きやすさを損なわないため、慣れない地形でも安心して歩けるという点で大きなメリットがあるからです。
登山に慣れていない方の場合、岩場や凸凹のある道などでバランスを取るのが難しく感じることがありますが、ミッドカットであれば足首をしっかりホールドしつつ、自由な足運びも可能です。
例えば、日帰りで行けるような低山やハイキングレベルの登山、あるいは標高がそれほど高くない山道を歩くといったシーンでは、ミッドカットの登山靴が最もバランスの取れた選択となるでしょう。
ローカットはいつ履く?
足首の自由度が高いため、軽快に歩けるという大きな利点があります。平坦な道や舗装された遊歩道などでは、より自然な歩き方ができるため、快適な歩行が可能です。ただし、その一方で足首のサポート力はほとんど期待できないため、不整地や岩場などでは捻挫などのリスクが高まります。この点には十分な注意が必要です。
また、軽量で持ち運びやすく、通気性にも優れているため、気温が高い季節や長距離を歩かない場合の選択肢としても有効です。例えば、旅行や街歩き、または標高の低い場所でのハイキングなどでは、ローカットの登山靴が活躍します。靴の脱ぎ履きも容易であるため、休憩の際や屋内との出入りが多いシーンでも便利です。
このように、ローカットは短時間の軽登山やウォーキング、旅行時などに適したモデルといえます。使用する場面をよく考え、足元の安全性と快適性を両立できるような選び方を心がけることが大切です。
何センチ大きいサイズがいい?
ワークマン女子の店舗で購入した登山靴、「トレックシューズアジム」なのだ。
— ワクイさん (@REyGEF9H7vbD6d2) April 1, 2024
足首をしっかりホールドしてくれるかんじで歩きやすかったのだ。
24.5が最小サイズで、レディースサイズはないのだ😅 pic.twitter.com/9I0o2YUbeU
登山靴を選ぶ際には、日常的に履いている靴のサイズよりも0.5cm〜1.0cm程度大きめのサイズを選ぶことが基本とされています。これは、特に下り坂を歩く際に足が前方へ滑り、つま先が圧迫されて痛みやトラブルの原因になることを防ぐための工夫です。
例えば、普段の靴のサイズが25.0cmの方であれば、25.5cmから26.0cm程度の登山靴を選ぶと適しています。また、登山では厚手の登山用ソックスを履くことが多いため、その分の余裕も考慮する必要があります。靴下によっては足のボリュームが増し、ピッタリサイズでは窮屈に感じることもあるため注意が必要です。
このため、登山靴を購入する際には必ず店舗で試し履きを行いましょう。その際には、足の指が自由に動かせるか、かかとがしっかりフィットしていて浮いてこないかなど、細かなフィット感を確認することが重要です。フィットしていない靴は靴擦れや疲労の原因にもなるため、慎重に選ぶことが快適な登山への第一歩です。
寿命は?・耐久性
登山靴新しくして、サバゲで荒っぽく使うのは別にしないと…と思ったところでワークマンの靴が使えるというツイートを見たので…
— ユニカ (@unica357) October 21, 2022
(買ったの一月以上前な気がする)
とにかく安いですね。
耐久性とか微妙かもだけど、とりあえず試してみます。 pic.twitter.com/pJ80xnJbnW
登山靴の寿命は一般的に3年〜5年程度とされています。ただし、これはあくまで目安であり、実際の寿命は登山靴の使い方や使用する頻度、登山する地域の気候や地形などによって大きく変わります。
例えば、月に1〜2回程度の頻度で比較的整備された登山道を歩く場合、4年以上にわたって問題なく使えるケースもあります。
一方で、毎週のように険しい山道や岩場などの厳しい環境で使用する場合は、2年を待たずして劣化が進み、ソールの摩耗や縫製部分のほつれ、クッション性の低下などが見られることもあります。
このように考えると、登山靴の寿命を少しでも長く保つためには、使用後の丁寧なメンテナンスが欠かせません。具体的には、使用後に汚れを落とし、風通しの良い場所でしっかりと乾かすこと、直射日光や高温多湿を避けた保管方法を心がけることが重要です。
これらの工夫によって、靴の素材の劣化を遅らせることができ、結果的に長く快適に履き続けることが可能になります。
ワークマンプラス登山靴の選び方:総括
以下にポイントをまとめました。
• トレッキングシューズは複数モデル展開されており、用途に応じた選択が可能
• アクティブハイクは軽量で初心者にも扱いやすいモデル
• アジムは防水性と耐久性を備えた中級者向けの設計
• エンリルは通気性が高く夏場の登山に適している
• 各モデルは防水性・通気性・グリップ力など異なる特徴を持つ
• 独自のアウトソール設計で滑りにくく安全性が高い
• ミッドソールにはクッション性の高い素材が使用されている
• DEOPUTインソールが抗菌防臭効果を発揮し衛生的
• ハイカットは足首を守り本格的な登山に適する
• ミッドカットは初心者に最適なバランスの良い仕様
• ローカットは軽登山やハイキング、街歩きにも向いている
• 登山靴は通常より0.5~1.0cm大きめのサイズ選びが基本
• 登山靴の寿命は使用頻度により大きく異なり、適切なメンテナンスが重要
• ゴアテックスのような防水透湿素材の選定が快適性を左右する
• 各モデルはワークマン プラス店舗またはオンラインで手軽に入手可能