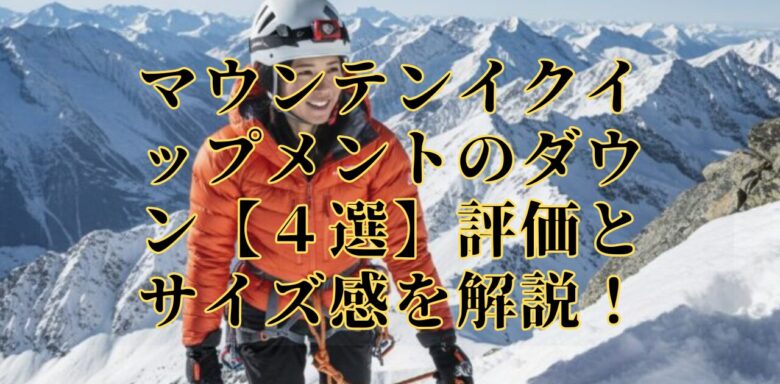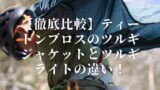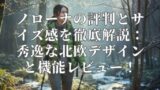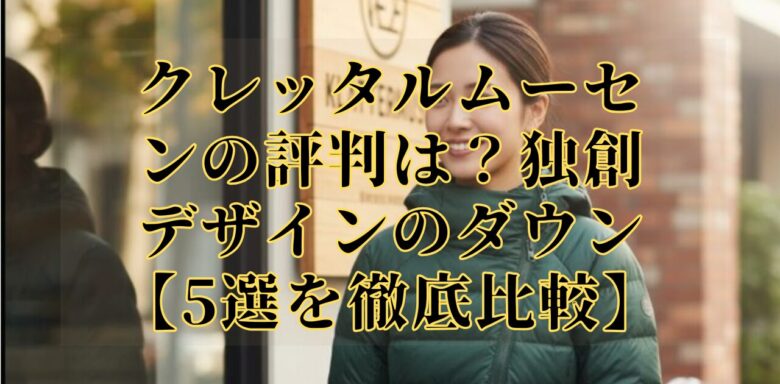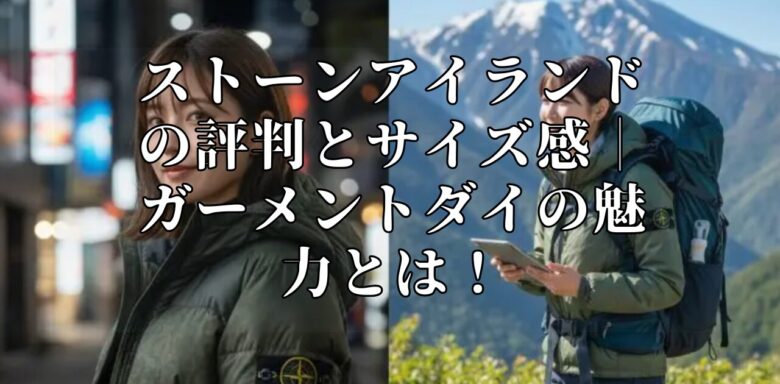マウンテンイクイップメントのダウンジャケットは、その高い評価と魅力から多くの登山者やアウトドア愛好家に支持されています。しかし、海外ブランドならではのサイズ感、例えば175㎝・65㎏の男性やレディース160㎝の女性がどのサイズを選ぶべきか、悩む方も少なくありません。
この記事では、ダウンを選ぶ際のポイントから、主要4モデルである①センヤ・ジャケット、②アースライズ・ジャケット、③ベガジャケット、そして④クラウドデュベの特徴とレビューを詳しく掘り下げます。4つを比較・違いを明確にし、登山で使う際の適性まで、マウンテンイクイップメントのダウンに関する評価とサイズ感の疑問に答えていきます。
この記事でわかること
①ブランドの歴史とダウン製品の強み
②体型別の具体的なサイズ感の目安
③主要4モデルのスペックと適したシーン
④モデルごとの保温力と耐候性の違い
マウンテンイクイップメントのダウン:評価とサイズ感の基礎

✅マウンテンイクイップメントのダウンとは 評価と魅力
✅ダウンジャケットを選ぶ際のポイント
✅サイズ感175㎝・65㎏レディース160㎝
マウンテンイクイップメントのダウンとは:評価と魅力
マウンテンイクイップメント(Mountain Equipment)は、1961年にイギリスのマンチェスター郊外で誕生したアウトドアブランドです。その歴史は、クライマーであったピーター・ハッチンソン氏とピート・クルー氏がシュラフ(寝袋)とダウンスーツを作り始めたことからスタートしました。
彼らの作る製品は非常に品質が高く、イギリスのヒマラヤ遠征隊にも供給されるなど、過酷な環境下での信頼性を早期から確立していたのです。
このように、ダウン製品の開発から始まったブランドであるため、現在展開されているダウンジャケットにもその技術と経験が色濃く反映されています。マウンテンイクイップメントのダウンが持つ評価と魅力は、主に以下の点に集約されます。
高品質なダウンと独自の構造
マウンテンイクイップメントの製品は、700フィルパワーや800フィルパワーといった高品質なグースダウンを積極的に採用しています。フィルパワーとは、ダウンの膨らむ力を示す数値で、この数値が高いほど少ない量で多くの空気(デッドエア)を蓄え、高い保温性を発揮します。
また、モデルによってはシュラフの構造を活かした「バッフル構造」(ダウンを箱状の隔壁に入れる構造)を採用しており、ダウンの偏りを防ぎ、コールドスポット(熱が逃げやすい部分)を最小限に抑える工夫がなされています。
耐候性に優れたシェル素材
多くのモデルで採用されている「DRILITE® Loft(ドライライトロフト)」は、マウンテンイクイップメント独自の完全防風・耐水性素材です。この素材は、外部からの雪や雨を防ぎつつ、内部の湿気を逃がす透湿性も備えています。ダウンの最大の弱点である「濡れ」から中綿を守ることで、天候が変わりやすい山岳地帯でも保温力を維持し続けることができます。
ブランドの原点:
ダウンシュラフとダウンスーツの開発から始まった歴史が、現在の高品質なダウンジャケットの基盤となっています。極地探検で培われた信頼性は、一般の登山シーンにおいても絶大な安心感をもたらします。
ジャケットを選ぶ際のポイント
マウンテンイクイップメントのダウンジャケットを選ぶ際、どのモデルが自分に合っているか判断するために、いくつかの重要なポイントがあります。デザインや色だけでなく、以下のスペック(仕様)に注目することで、ご自身の目的に最適な一着を見つけることができます。
保温力(フィルパワーとダウン量)
保温力を左右する最大の要素は「フィルパワー」と「ダウン量」です。
- フィルパワー(FP): 前述の通り、ダウンの「質」を示します。800FPのように数値が高いほど高品質で、軽量ながら高い保温性を持ちます。
- ダウン量(g): 実際にジャケットに封入されているダウンの「量」です。数値が大きいほど、単純な保温力は高くなります。
例えば、同じ700FPのダウンでも、ダウン量が150gのモデルと250gのモデルでは後者の方が暖かくなります。ご自身の使用シーン(夏山か冬山かなど)に合わせて、必要な保温力を見極めることが重要です。
シェル素材(デニール数と機能性)
シェル素材は、ダウンを保護し、耐候性を決定づける部分です。注目すべきは「デニール(dn)」という糸の太さを示す単位と、素材の機能性です。
- デニール数: 10dnや20dnのように数値が小さいほど薄く軽量ですが、耐久性は低下します。逆に40dnや50dnになると、生地が厚くなり耐久性や防風性が増しますが、重量は重くなります。
- 機能性: DRILITE® Loftのような防風・耐水素材か、あるいは軽量性重視の薄手リップストップナイロンかによって、適した天候が変わります。
構造(バッフル構造 vs ステッチスルー構造)
ダウンの保温効率は、その構造によっても変わります。
- バッフル構造: ダウンを箱(バッフル)で仕切る構造です。縫い目からの放熱(コールドスポット)が少なく、ダウンの膨らみを最大限に活かせるため、保温性が非常に高いのが特徴です。厳冬期モデルに多く採用されます。
- ステッチスルー構造: 表地と裏地を直接縫い合わせる構造です。製造が容易で軽量・コンパクトに仕上がりますが、縫い目部分がコールドスポットになりやすいデメリットがあります。夏山用や中間着モデルに多く見られます。
選ぶ際の3つの着眼点
ダウンジャケット選びで失敗しないためには、「保温力(FPとダウン量)」「耐候性(シェル素材)」「保温効率(構造)」の3点を、ご自身の「使用シーン(いつ、どこで使うか)」と照らし合わせることが最も大切です。
サイズ感175㎝・65㎏ レディース160㎝

マウンテンイクイップメントのダウンジャケットを選ぶ上で、最も悩ましいのがサイズ感です。このブランドはイギリス発祥のため、サイズ表記が「EUサイズ(ヨーロッパサイズ)」を基準にしていることが多く、日本の「JPサイズ」とは感覚が異なります。
EUサイズとJPサイズの関係
基本的な目安として、マウンテンイクイップメントのEUサイズ「S」は、JPサイズ(日本規格)の「M」に相当します。同様に、EU「M」はJP「L」に近くなります。購入時は、タグに記載されているのがどちらのサイズ表記かを必ず確認してください。
男性:身長175cm・体重65kgの場合
身長175cm・体重65kgの標準的な体型の男性の場合、多くのアウトドアブランドでJP「M」か「L」を選ぶことが多いかと思われます。
- EU「S」サイズ (JP「M」相当):
ジャストフィットで着たい場合、中間着(ミドルレイヤー)としてシェルの下に着込むことを想定する場合は、このサイズが適している可能性が高いです。マウンテンイクイップメントは肩周りや胸囲に比較的ゆとりがある設計のモデルが多いとされていますが、ウェストは細身のシルエットになる傾向があります。 - EU「M」サイズ (JP「L」相当):
アウターとして、内側に厚手のフリースなどを着込む余裕が欲しい場合は、こちらのサイズがおすすめです。袖丈や着丈はやや長めになる可能性があります。
女性:身長160cmの場合
身長160cmの標準的な体型の女性の場合、JP「S」か「M」を選ぶことが多いでしょう。
- EU「XS」サイズ (JP「S」相当):
タイトすぎず、程よいフィット感で着用できる可能性が高いサイズです。薄手のフリース程度なら着込めるゆとりがある場合が多いです。 - EU「S」サイズ (JP「M」相当):
ゆったりと着たい場合や、内側にしっかり着込むことを想定する場合は、このサイズが選択肢になります。袖が長くなる可能性があるため、袖口のベルクロ(マジックテープ)で調整できるモデルか確認すると良いでしょう。
サイズ選びの注意点
ここで紹介したサイズ感は、あくまで一般的な目安です。モデルのデザイン(細身か、ゆったりめか)や、個人の体型(肩幅が広い、腕が長いなど)、そして「どのように着たいか(ぴったりか、ゆったりか)」によって最適なサイズは変わります。
可能であれば、必ず店頭で試着することを強くおすすめします。
【徹底比較 】マウンテンイクイップメントのダウン:評価とサイズ感

✅①環境配慮と汎用性を両立する:アースライズ・ジャケット
✅②耐水圧と透湿性を備えたダウン:センヤ・ジャケット
✅③過酷な環境下での使用を前提:ベガジャケット
✅④軽量と保温を両立させたフラッグシップ:クラウドデュベ
✅4つを比較・違い
✅登山での活用シーン・メリットとデメリット
✅まとめ:マウンテンイクイップメントのダウン|評価とサイズ感
①環境配慮と汎用性を両立する:アースライズ・ジャケット

アースライズ・ジャケットは、マウンテンイクイップメントのラインナップにおいて、「環境への配慮」と「汎用性の高い軽量性」という2つの現代的なニーズを見事に両立させたモデルとして、高い評価を得ています。環境負荷を最小限に抑えたいと願う登山者から、装備の軽量化を追求するクライマーまで、幅広い層に支持されている一着です。
最大の特徴:100%リサイクル素材による構成
このジャケットが持つ最大の特徴は、製品を構成する主要な素材が、そのすべてにおいてリサイクル資源から作られている点にあります。具体的には、シェル(表地)とライニング(裏地)には、使用済みのペットボトルなどを原料とする100%リサイクルのポリエステル生地が採用されています。
さらに、保温材である中綿には、回収されたダウン製品から洗浄・再生された100%リサイクルダウンが使用されています。このリサイクルダウンは、650フィルパワーから700フィルパワーという十分な膨らみ(ロフト)を持っており、新品のダウンに遜色ない実用的な保温力を確保しています。
まさに、環境保全への強い意志を製品全体で体現したモデルと言えるでしょう。
保温効率と軽量性を両立するハイブリッド構造
アースライズ・ジャケットは、保温構造においても工夫が凝らされています。基本的な構造は、表地と裏地を直接縫い合わせることで軽量かつコンパクトに仕上げられる「ステッチスルー構造」を採用しています。これにより、中間着としても着ぶくれしにくい、しなやかな着心地を実現しました。
ただ、それだけではなく、特に保温性が求められる胴体部分などには、ダウンの偏りを抑えるための「ナローバッフル構造」(幅の狭い隔壁)をハイブリッドで採用しているとされています。この組み合わせが、約390g(フードなしモデル)から約440g(フード付きモデル)という軽量性を達成しながらも、効率的に体温を保持する設計の秘密です。
ライターの視点:最適な使用シーン
アースライズ・ジャケットの真価は、その汎用性の高さにあります。例えば、「夏山登山の防寒着」として携行するのに最適です。山頂での休憩時や、日が落ちて急に冷え込む朝晩のテント場などで、バックパックからさっと取り出して羽織るのに役立ちます。
非常に軽量で、付属のスタッフサック(またはハンドポケット)に小さく収納できるため、荷物の容量を圧迫しない点も大きなメリットです。
また、アルパインクライミングや沢登りなどでの「ビレイ(確保)時の保温着」としても活躍します。冬場には、ハードシェルの内側に着込む「中間着(ミドルレイヤー)」としても優秀で、ステッチスルー構造のしなやかさが動きを妨げません。
アースライズ・ジャケットの注意点
このモデルを選ぶ上で最も注意すべき点は、耐候性です。シェル素材は軽量性を重視したリサイクルポリエステルであり、表面には耐久撥水(DWR)加工が施されていますが、これはあくまで一時的なものです。センヤ・ジャケットなどに採用されている「DRILITE® Loft」のような完全防風・耐水性の生地ではありません。
そのため、本格的な雨や湿った雪が降る状況下で、アウターとして単体で着用し続けるのは避けるべきです。保温力が急速に失われる危険があります。天候が悪化した場合は、必ず上からレインウェアやハードシェルを重ね着することを前提として使用してください。
②耐水圧と透湿性を備えたダウン:センヤ・ジャケット

センヤ・ジャケットは、マウンテンイクイップメントのラインナップにおいて、「保温力」と「耐候性」という、冬のアクティビティで求められる2大要素を非常に高いレベルで両立させた、信頼性の高いダウンジャケットです。特に、天候の変動が予想される中でも、アウターとして安心して使い続けられる堅牢さが魅力となっています。
強み1:強固な耐候性を生む「DRILITE® Loft 40dn」
このモデルが持つ最大の特徴は、シェル素材(表地)にマウンテンイクイップメント独自の高機能素材「DRILITE® Loft 40dn」を採用している点にあります。これは、高い耐水圧と透湿性を備えた、完全防風・耐水性の素材です。この強固なシェルが、ダウンの最大の弱点である「濡れ」を物理的にブロックします。
また、「40デニール(dn)」という数値は、生地の糸の太さを示しています。例えば10dnや20dnといった軽量性を追求したモデルと比較して、厚手で非常に丈夫であることを意味します。
そのため、雪や雨、強風から中綿のダウンを守るだけでなく、冬のキャンプでの設営作業や、登山道での岩・枝などとの擦れに対する「耐久性」も高く、タフに扱える安心感があります。
強み2:ステッチスルー構造を補う豊富なダウン量
センヤ・ジャケットの保温構造は、表地と裏地を直接縫い合わせる「ステッチスルー構造」を採用しています。これは製造が比較的容易で、軽量かつしなやかに仕上がるメリットがある一方で、縫い目部分がコールドスポット(熱が逃げやすい点)になりやすいという側面も持ちます。
しかし、センヤ・ジャケットはこの弱点を補うために、700フィルパワーの高品質ダウンを「約220g」という豊富な量で封入しています。これは、他の軽量ダウンジャケットと比較しても非常に多いダウン量です。
この圧倒的なダウンの量が、縫い目部分を内側からロフト(かさ高)で覆い隠すように機能し、コールドスポットからの放熱を最小限に抑制します。結果として、ステッチスルー構造でありながらも極めて高い保温力を発揮するのです。
センヤ・ジャケットの強み:アウターとしての完結力
このモデルは、「天候を問わず、確実に暖かいダウンがアウターとして欲しい」というニーズに完璧に応えます。強固なシェルが雪や風を防ぎ、豊富なダウンが体温を維持するため、例えば「冬の低山登山」や「雪中キャンプ」といったシーンで、上にハードシェルを羽織らなくても、この一着で完結できる対応力の高さが最大の強みです。
知っておきたい注意点
一方で、デメリットも存在します。それは「重量」です。約220gという豊富なダウン量と、40デニールの堅牢なシェルを採用しているため、総重量は約580g(データB参照)となります。アースライズ(約390g)やクラウドデュベ(約325g)のような軽量性・コンパクト性を最優先するモデルと比較すると、ずっしりとした重さを感じます。
また、構造はステッチスルーであるため、厳冬期の高所登山などで使用される本格的な「バッフル構造」採用モデルと比較した場合、極低温下での保温効率では一歩譲る可能性があります。携帯性よりも、着用時の絶対的な安心感を優先するモデルと言えるでしょう。
③過酷な環境下での使用を前提:ベガジャケット

ベガジャケットは、マウンテンイクイップメントのダウン製品群の中でも、特に「テクニカルな使用」に焦点を当てた高性能モデルです。具体的には、アイスクライミングや冬期アルパインクライミング、雪稜登山など、寒さの中で高い運動量と繊細な道具操作が求められる、最も過酷な環境下での使用を前提に設計されています。
センヤを凌ぐ軽量性と保温性
このジャケットの大きな特徴として、まずシェル(表地)には、前述の通り、高い防風・耐水性を誇る「DRILITE® Loft」が採用されています。これにより、クライミング中に遭遇する雪や風、氷の付着から中綿のダウンを確実に守り、保温力の低下を防ぎます。
さらに注目すべきは、中綿の品質です。センヤ・ジャケットが700フィルパワーのダウンを採用しているのに対し、ベガジャケットはさらに高品質な「800フィルパワー」のグースダウンを「約235g」と豊富に封入しています。フィルパワーが高いほど、少ない重量で多くの空気を含むことができます。
つまり、ベガジャケットは、センヤ・ジャケットと同等以上の高い保温力を持ちながらも、より「軽量」に仕上がっているのです。これは、少しでも装備を軽くしたいアルパインクライミングにおいて、非常に大きな利点となります。
「動く」ことを前提としたクライミング機能
ベガジャケットが「プロユース」として信頼されている最大の理由は、その細部にまで盛り込まれたクライミング仕様の機能性にあります。
- ヘルメット対応フード:
冬期登山やクライミングではヘルメットの着用が必須です。ベガジャケットのフードは、ヘルメットの上からでも問題なく被れるように大型に設計されています。同時に、視界を妨げないよう調整する機能も充実しており、安全な行動をサポートします。 - ハーネスに干渉しないポケット配置:
クライミング時には腰にハーネス(安全ベルト)を装着します。一般的なジャケットの腰ポケットはハーネスに隠れてしまい、全く使えなくなってしまいます。ベガジャケットは、ポケットの位置を通常より高い位置(胸部に近い位置)に設定することで、ハーネス装着中もハンドウォーマーポケットとして機能するように作られています。 - ダブルジッパー(2ウェイ・フロントジッパー):
フロントのジッパーが下からも開けられる仕様になっています。これは、ハーネスに接続したビレイデバイス(確保器)を操作する際に、ジャケットの裾をまくり上げることなく、ジッパーを「下から開ける」だけでスムーズにアクセスできるようにするためです。
プロユースの信頼性:4つの要素の高次元バランス
ベガジャケットは、「軽量性(800FPダウン)」「保温性(ダウン量約235g)」「耐候性(DRILITE® Loft)」「運動性(クライミング仕様の機能・裁断)」という、冬期登山で求められる4つの要素を極めて高い次元でバランスさせています。
例えば、冬の八ヶ岳でのアイスクライミングや、北アルプスの雪稜登山といったシーンでは、アプローチでの行動、ビレイ(確保)中の停滞、急な天候悪化、そして氷壁を登るテクニカルな動きのすべてに対応しなくてはなりません。このような厳しい要求に応えられるからこそ、多くの経験豊富なクライマーから高い評価を得ているのです。
知っておきたい点
これだけの高性能モデルであるため、価格も相応に高価になる傾向があります。また、その機能性は冬期クライミングに特化しているため、例えば雪中キャンプでのリラックスタイムや、風のない穏やかな低山ハイクがメインであれば、オーバースペック(過剰な性能)となる可能性もあります。ご自身の主な活動領域を見極めて選ぶことが大切です。
④軽量と保温を両立させたフラッグシップ:クラウドデュベ

クラウド・デュベ(Duvet)は、その「雲(Cloud)」という名の通り、マウンテンイクイップメントのラインナップの中で圧倒的な軽量性と抜群の保温力を両立させた、フラッグシップモデルの一つです。このジャケットは、行動中に着ることを目的としたものではなく、主に冬のテント泊や雪山縦走など、活動を停止している「停滞時」の保温着として最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。
驚異的な「重量対保温性」の比率
このモデルの核心は、その驚くべきスペックにあります。総重量はわずか約325g(データB参照)と、今回比較するモデルの中では最軽量クラスです。しかし、驚くべきはその中身です。中綿には、高品質な800フィルパワーの撥水ホワイトグースダウンが「約180g」も封入されています。
つまり、ジャケットの総重量325gのうち、実に半分以上(約55%)が保温材であるダウンそのもので構成されている計算になります。この極めて高いダウン比率こそが、クラウドデュベが「桁違いの暖かさ」と評される最大の理由です。
軽量性を支える極薄シェルと撥水ダウン
総重量の軽量化を実現するため、シェル素材(表地)には10デニールという非常に薄く、軽量な生地が使用されています。この極薄生地は、軽量性だけでなく、しなやかな着心地と、付属の収納袋に驚くほど小さく圧縮できる「コンパクト性」にも大きく貢献しています。
また、中綿のダウンには撥水加工が施されています。これは、ダウンが濡れるとロフト(かさ高)が失われ、保温力が無くなってしまうという最大の弱点を克服するための機能です。
特に冬のテント内は、人間の呼吸や雪の付着などで結露が発生しやすい環境です。このような状況でダウンがわずかに湿気を含んでも、撥水ダウンであればロフトが潰れにくく、保温力の低下を最小限に抑えてくれる強みがあります。
ダウンの膨らみを最大限に活かす設計
クラウドデュベは、封入された800FPダウンの膨らみを最大限に活かすための構造設計がなされています。着用すると、縫い目による拘束が少ないため、ダウンが瞬時に膨らみ、体温を逃さず暖かい空気の層(デッドエア)を確保します。羽織ってすぐに暖かさを感じられるのは、この優れたロフト復元力によるものです。
クラウドデュベが輝く「停滞」シーン
このジャケットの真価が発揮されるのは、運動を停止し、体温が奪われ始める瞬間です。例えば、厳冬期のテント場での設営後や食事中、雪山縦走での長めの休憩、あるいは山小屋でのリラックスタイムなど、「保温の切り札」としてバックパックに忍ばせておくのに最適な一着です。
クラウドデュベの明確な注意点(デメリット)
このジャケットのメリットは、そのままデメリットと表裏一体です。まず、「耐久性の低さ」は最大の注意点です。10デニールのシェルは、岩角、木の枝、ピッケルやアイゼンの先端など、鋭利なものに引っ掛けると非常に破れやすいです。焚き火などの火の粉も絶対に避けなければなりません。
次に、「行動着ではない」という点を厳守する必要があります。これほど暖かいダウンを着て行動すれば、確実に大量の汗をかきます。撥水ダウンとはいえ、汗による内側からの濡れ(汗濡れ)は防ぎきれず、休憩時に汗が冷えることで、かえって低体温症のリスクを高める危険性があります。
最後に「耐候性の低さ」です。シェルは耐水性・防風性が低いため、風雪にさらされる状況でアウターとして使用することはできません。基本的には「アウターシェル(ハードシェル)の内側に着込む」か、「風のない穏やかなテント場や山小屋の中」で使用することを前提とした、デリケートかつパワフルな保温着です。
4つを比較・違い
これまで紹介した4つの主要モデル「アースライズ」「センヤ」「ベガ」「クラウドデュベ」は、それぞれ異なる目的を持って設計されています。ご自身の登山スタイルに合わせて選ぶために、ここでスペックと特徴を比較してみましょう。
| モデル名 | アースライズ・ジャケット | センヤ・ジャケット | ベガジャケット | クラウド・デュベ |
|---|---|---|---|---|
| 主な用途 | 夏山/中間着/クライミング | 冬の低山/雪中キャンプ | 冬期登山/アルパインクライミング | 冬のテント泊/停滞時保温着 |
| 保温力 (FP) | 中 (650-700FP) | 高 (700FP) | 高い (800FP) | 非常に高い (800FP) |
| ダウン量 | 少なめ (約107-143g) | 多い (約220g) | 多め (約235g) | 中程度 (約180g) |
| 耐候性 (シェル) | 低い (撥水程度) | 高い (DRILITE® Loft 40dn) | 高い (DRILITE® Loft) | 低い (軽量性重視 10dn) |
| 重量 | 非常に軽量 (約360-440g) | 中程度 (約580g) | 中程度 (データ参照) | 最軽量クラス (約325g) |
| 特徴 | 100%リサイクル素材 | 耐候性と保温力のバランス◎ | クライミング仕様・高機能 | 圧倒的な軽量保温比 |
※重量やダウン量はモデルやサイズ、年度によって変動する場合があります。
この表から分かるように、「耐候性(濡れへの強さ)」を重視するならセンヤかベガ、「軽量性」を最優先するならクラウドデュベかアースライズ、という選択になります。ベガはクライミングなど運動量が多いシーン、クラウドデュベは停滞時、と使い分けるのが理想です。
登山での活用シーン・メリットとデメリット
マウンテンイクイップメントのダウンジャケットを登山で使用する場合、それは単なる「防寒着」ではなく、時には命を守る「装備(イクイップメント)」として機能します。そのため、そのメリットと、重大な注意点(デメリット)を正確に理解しておくことが非常に重要です。
登山における強力なメリット
マウンテンイクイップメントのダウンが登山者に選ばれる理由は、その圧倒的な信頼性にあります。
歴史に裏打ちされた保温性:
ブランドの歴史が極地探検と共に歩んできたことからも分かる通り、その保温性は折り紙付きです。万が一のビバーク(緊急野営)や行動不能に陥った際、体温を維持するための「生命線」となり得る安心感を与えてくれます。
日本の気候への適応(DRILITE® Loft):
前述の通り、センヤ・ジャケットやベガジャケットに採用されている「DRILITE® Loft」は、完全防風・耐水性を備えています。
これは、乾いた雪(ドライスノー)が中心の海外大陸性と異なり、湿った雪(ウェットスノー)が多い日本の冬山において、非常に大きな強みとなります。天候が急変しても、ある程度の雪や風であればアウターとして機能し続ける対応力を持ちます。
軽量化による安全性向上:
クラウドデュベのような800フィルパワー採用モデルは、最高の「重量対保温性」を提供します。これは、荷物の軽量化(ウルトラライト)を目指す登山者だけのメリットではありません。
バックパックが軽くなれば、登山中の疲労が軽減され、結果として転倒や判断ミスのリスクを減らすことにつながり、すべての登山者の安全性を向上させる強力な武器となります。
ダウン製品共通のデメリットと「濡れ」の危険性
一方で、マウンテンイクイップメント製品に限らず、ダウンには共通する最大の弱点が存在します。それは、「濡れ」に極めて弱いという点です。ダウンは一度濡れてしまうと、羽毛が潰れて空気の層(デッドエア)を保持できなくなり、保温力を急速に、そしてほぼ完全に失います。
この「濡れ」には、外からと内からの2種類があり、両方を理解する必要があります。
1. 外からの濡れ(雨・雪)
DRILITE® Loft採用モデル以外、例えばアースライズやクラウドデュベのような軽量性を重視したモデルは、シェル素材の耐水性が高くありません。そのため、雨や湿った雪に長時間さらされると、生地が水分を含み、やがて中綿のダウンまで濡れてしまいます。
これを防ぐためには、天候が崩れたら「すぐにレインウェア(ハードシェル)を上から羽織る」ことが絶対条件です。近年は撥水ダウンも増えていますが、これはテント内の結露などの「湿気」に耐えるためのものであり、雨や雪を完全に防ぐ防水機能ではありません。濡らさない努力が最も重要です。
2. 内からの濡れ(汗=汗濡れ)
これは、特に登山初心者が陥りやすい、最も危険な罠の一つです。登山中に「寒い」と感じてダウンジャケットを着てしまうと、登りの運動量で体温が急上昇し、確実に大量の汗をかきます。
その汗(湿気)はダウンジャケットの内側からダウンに吸収されてしまいます。そして、休憩するために立ち止まった瞬間、体は急激に冷やされ、汗で濡れたダウンが体温を奪い始めるのです。これは「汗冷え」と呼ばれ、冬山では低体温症に直結する非常に危険な状態です。
登山での正しい使い方:保温の「切り札」として使う
この「汗濡れ」を防ぐため、登山におけるダウンジャケットの使い方は、セオリー(定石)が確立されています。
- 行動中(Active)は着ない:
行動中は、ベースレイヤーと、フリースや化繊インサレーション(化学繊維の中綿)といった「濡れても保温性が落ちにくい」行動着(アクティブインサレーション)で体温を調整します。 - 休憩中(Static)にのみ着る:
ダウンジャケットは「静的保温着(スタティックインサレーション)」、つまり「保温の切り札」として温存しておきます。 - 正しい着用タイミング:
休憩場所に着いたら、寒いと感じる前に、すぐにバックパックからダウンを取り出し羽織ります。さらにその上からハードシェル(レインウェア)を着ることで、風を完全にシャットアウトし、ダウンが蓄えた熱を一切逃がさず、効率的に体を休ませることができます。
このように、「行動着」と「保温着」を明確に使い分けることが、マウンテンイクイップメントのダウンの性能を最大限に引き出し、安全な登山を行うための鍵となります。
まとめ:マウンテンイクイップメントのダウン|評価とサイズ感
マウンテンイクイップメントのダウンジャケットに関する評価とサイズ感について、重要なポイントをまとめました。
- マウンテンイクイップメントはシュラフ開発から始まった信頼性の高いブランド
- ダウン選びのポイントは「保温力」「シェル素材」「構造」の3点
- サイズ感はEU規格が基本でJP規格よりワンサイズ大きめ
- EU「S」サイズがJP「M」サイズに相当すると考えるのが目安
- 175cm 65kg男性はジャストならEU「S」、ゆとりを持つならEU「M」
- 160cm女性はフィット感重視ならEU「XS」、標準ならEU「S」が目安
- サイズ感はモデルや体型、好みで変わるため試着が最も確実
- アースライズ・ジャケットはリサイクル素材を使用した軽量モデル
- アースライズは夏山や中間着に適している
- センヤ・ジャケットはDRILITE® Loft採用で耐候性と保温性を両立
- センヤは冬の低山や雪中キャンプのアウターに最適
- ベガジャケットは800FPとDRILITE® Loftを組み合わせた高機能モデル
- ベガは本格的な冬期登山やクライミング向け
- クラウドデュベは800FP撥水ダウンを使用した超軽量・高保温モデル
- クラウドデュベはテント泊など停滞時の保温着として最強クラス
- 耐候性重視なら「センヤ」か「ベガ」
- 軽量性重視なら「クラウドデュベ」か「アースライズ」
- ダウンは濡れると保温力を失うのが最大の弱点
- 登山ではレインウェアとの併用が必須
- 行動中にダウンを着るのは汗濡れのリスクがあるため非推奨